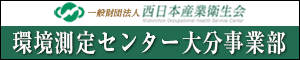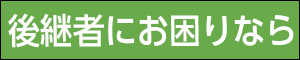深刻さを増す建設業
2025年05月16日
新庁舎建設を巡って、東京都世田谷区と、工事を請け負った大手ゼネコンが深刻なトラブルになっている。当初計画の2027年10月の完成が29年4月にずれこんだのが発端だった。同区はゼネコンに対し、工事遅延は契約に反するなどとして17億円超の違約金を求めるとともに、2年間の指名停止の処分を下した▼大手ゼネコンの肩を持つ気などない。違約金はゼネコンに課せられることになっているが、最終的に背負うのは下請けに入っている中小の業者であろう。何かあれば、利幅を削られるなど下請けにしわ寄せが及ぶ構図は、今に始まった話ではないとはいえ、心が痛む▼行政はどれほど建設業界の現状を把握しているのだろうか。今日の建設業界が直面しているのは、物価高と人手不足という「複合災害」である。国土交通省の集計では、建設資材価格は20年以降、平均で35%以上も上昇した。特に鋼材はピーク時で2倍近くに跳ね上がり、輸送費や人件費も高騰。現場の見積もりには、今や「予知能力」が求められるようなありさまである▼人手不足も深刻だ。建設業の技能労働者の平均年齢は50歳代を超える。熟練工たちが定年世代となり続々と一線から退いているというのに、若い人材はなかなか入ってこない。尋常でない物価高と人手不足。万博工事などの大規模事業、東京一極集中の加速という、いずれも国策がもたらした帰結であろう▼帝国データバンクの集計では、昨年の「建設業」倒産件数は過去10年で最悪の1890件に上った。従業員数別でみると、「10人未満」が92%を占める。弊紙8日付紙面に、大建協宇佐支部総会で久綱信一支部長が「適正利潤」を訴えたという記事が出ていた。断じて利益追求などではない。「持続可能な建設業」を守るための、悲痛の叫びである。(熊)