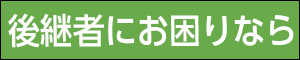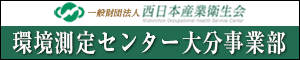避難ルート
2025年07月14日
県の土木未来教室は、ご存じのように土木の仕事や魅力、防災について小中学生に知ってもらうための取り組みの一つ。県建設業協会各支部などの協力のもと、実際に工事現場を訪れ、重機操作を体験できるのも人気だ。「将来は土木の仕事に就いてみたい」と言う生徒もいるから、ある程度の成功実績を上げているようだ▼先日は、中学生を対象にした防災学習を取材した。最初に土砂災害や水害の仕組みについて学び、次に5班に分かれて土砂災害警戒区域や浸水想定範囲などを歩き、避難所までのルートにおける注意点を調べ、最後にそれらを地図上に落とし込むという内容だ。フィールドワークには、県土木事務所OBからなる砂防ボランティア3人が同行し、詳しい説明を受けながら歩いた▼オリジナルマップづくりは、危険想定区域を色分けし、安全かつスムーズに避難できるルートを考えるのが狙いだ。崩れた土砂は高さの2倍まで広がることや、なるべく川から離れて歩けるか、自動車でも通りやすいかなど、生徒らが学んだことを持ち寄って共同でマップを仕上げていく。開始前は、ハザードマップ作成は荷が重いのではと思ったが、想像以上に本格的なものが完成。班ごとの発表では、おススメの避難ルートに対して疑問の声が上がるなど、真剣に取り組んでいることが伺えた▼教頭は「きょうでまちを見る目が少し変わったかな。災害から自分や家族を守るために、どんな力が必要か、将来のためにも学んでほしい」と話した▼災害は、いつ、どこで起きるかわからない。自宅にいる時とは限らないのだ。ハザードマップで自宅周辺だけでなく、学校や職場、よく行く場所についても知っておく必要がある。何よりも、命を守るための避難ルートを調べる目を養うことが大事だと思った。(コデ)