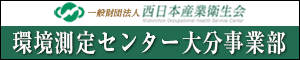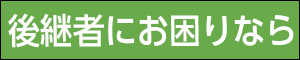下駄の雪
2025年10月14日
快挙である。大阪大特任教授の坂口志文さんが今年のノーベル生理学・医学賞に輝いた。人体の免疫反応の暴走を止める「制御性T細胞」の発見が評価された。体を守るはずの免疫機能だが、ときに体に侵入してきた病原菌以外のものまで排除しようとふるまうことがある。そうした動きに、制御性T細胞がブレーキをかけるという。まさに人体の知恵だ▼こちらには、そうした智恵はなかったようだ。公明党が自民・公明両党の連立政権からの離脱を表明し、四半世紀に及んだ協力関係はきしみを超えて一気に破断した。自民党総裁の地位を勝ち取った高市早苗氏がそのまま日本初の女性首相になると思われていたが、いきなり黄信号がともり、先行きはにわかに霞み始めた▼高市氏は「一方的」と公明の姿勢を批判したが、自らがまいた種と言えなくもない。裏金問題で厳しく批判を浴び、国政選挙で厳しい審判が下されたというのに、あたかも忘れたかのように裏金議員を党要職につけた。何よりも、当てつけるように、総裁選直後の会談相手に選んだのは、友党の公明ではなく、野党・国民民主の代表だった▼「踏まれても蹴られてもついて行きます下駄の雪」と揶揄された公明だったが、さすがに我慢の限界だったのだろう。この言葉、なかなか味わい深い。かつて「下駄の雪」とは、1990年代の連立相手の社会党(現・社民党)のことだった。雪は消えてなくなる…。なるほど野党第1党だった社会は先細った▼だが、今回の連立解消は違う。下駄そのものを壊しかねない。組織力で知られる公明の選挙協力が得られなくなる影響について、毎日新聞10月11日付紙面は「次期衆院選小選挙区で25~45人が落選危機」と報じた。空耳だろうか。こんな文句が聞こえてきた。下駄の消えゆく、雪どこへ。(熊)