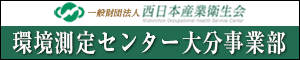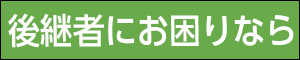対話
2025年10月15日
ラジオの番組「武田鉄矢 今朝の三枚おろし」で、話の通じない相手と話をする方法という話題を聞いた。十人十色と言うが、人はそれぞれ生まれも育ちも違うので考え方も違うのは当然のことだ。ましてや外国人となると風習や宗教などで日本人には想像できないほど違うのだ▼日本には「郷に入っては郷に従え」ということわざがあるが、これが通じるのは日本人だけである。最近のインバウンドの増加で外国人のマナーが問題となっているが、一昔前のバブル時代の日本人が海外旅行先で評判が悪かったのと同じ現象だ。もっとも、日本には「旅の恥はかき捨て」ということわざもあるが…▼このように見方を変えればお互いさまなのに、自分と違う考えの相手は間違っているという考えは相手から見ても同じで、到底理解し合うことは出来ない。これが紛争や戦争の原因となっているのではないだろうか▼話の通じない相手と話をする時は、相手がなぜそのような考えを持つようになったかを興味深く丁寧に聞くことから始まる。その背景が分かると、賛同はできないにしても理解することはできる▼今後さらにインバウンドは増えるだろうし、少子高齢化で外国人労働者に頼らざるを得なくなってくる。一昔前、人口減少が予想される中で、「社会保障制度や社会インフラを維持するためにはロボットか移民が必要」と言われたことがある。逆ピラミッド型の人口構成社会では支える人の方が支えられる人より圧倒的に少ない。介護人材も不足してきている▼日本が今後も生活水準を維持し、持続的発展を遂げるためには人口減少に歯止めをかけなければならない。政府は遅まきながら少子化対策に力を入れはじめたが、手っ取り早い方法として移民受け入れの制度設計など国民的議論が必要な時期が来ている。(筋)