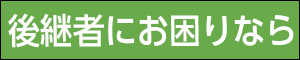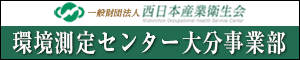クイ
2025年10月22日
昔の話になるが、警察担当の記者をしていたことがある。厄介だったのが「夜回り」。住所を頼りに警察官や関係者の自宅を訪ねるのだが、今のように住宅地図も完備されておらず、番地まで分かっても探しあぐねることもたびたび。住宅に地番表示がなければ、もうお手上げだった▼「ここは2番地だから、隣家はお目当ての3番地」と思って呼び鈴を押して、「10番地だよ」と聞かされてがくぜんとしたこともある。再開発で住所が付け替わり、合併で飛び番が生まれることも珍しくない。聞けば、ソウルなどは道路の起点から原則20㍍ごとに番号が振られているという。日本の住所はよく言えば柔軟。ありていに言えばいい加減なものだ▼「一丁目一番地」も簡単に動いてしまうらしい。公明党の連立離脱で始まった政局の混迷。一時は自民党の下野もささやかれたが、日本維新の会との連立で高市早苗政権が誕生した。「離れ業」である。なぜなら維新といえば、昨年9月に当時の馬場伸幸代表が「政策の一丁目一番地である政治改革」という文脈で、自民党にとっては受け入れがたい「政策活動費・企業団体献金の廃止」を訴えていたからだ▼連立に当たって維新が自民党に突きつけた12項目の要望の中で、政治改革は12番目。「一番地」から「十二番地」になってしまった。とってつけたように「議員定数削減」を言い出したが、「企業団体献金の廃止」は番外地といった状況だ。透けて見えるのは、政権入りという党利党略である▼「一丁目一番地」という言葉の響きにはどこか威勢の良さがある。だが地図の起点は本来、静かに地中に打たれたクイである。動かないからこそ信頼される。「女性初の首相」が立つ「一丁目一番地」は、どこに定められるのか。番地の看板よりも、クイの深さが問われている。(熊)