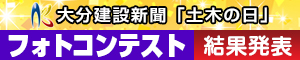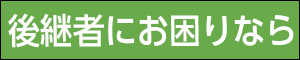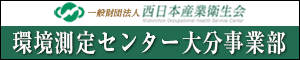忌み語
2025年10月29日
「そろそろお開きにしようか」。居酒屋での飲み会での終盤、しばしば耳にする言葉だ。よくよく考えれば奇妙な言葉遣いである。宴はおしまいなのに、「開く」というのである。「終わり」という忌み語を避けるために、わざわざそれとは真逆の言葉を使う。梨を「無し」に通じるからとして、「有りの実」と呼ぶのも同じである▼言葉に発すると、終わってしまったり、無(亡)くなってしまったりする事態が起きてしまうという、恐れが働くからであろう。結婚式で「別れる」「壊れる」という言葉がタブーとされるのも同様である。言葉に吉凶の手綱を結び、暮らしの安寧を祈る「言霊の国」ならではの作法であろう▼かつては山でも同じであった。東国では熊を「山の神」などと呼んでいた。名指しを避ける「呼称忌避」は、獣との境を荒らさず、同じ山地で共に生きるための知恵だったのだろう。だが今、神は荒ぶる。北国では人々が襲われ、朝日新聞の集計では今年度の死傷者は170人に上る。不安は濃くなり、熊は「神」から「あくま(悪魔)」に転じ、恐怖と憎悪の対象になっている▼西洋の魔女狩りではないが、ぼんやりした不安が人々を敵意に駆り立てる空気がつくり出されることがある。昨今の外国人を巡る議論もその一つである。共同通信の7月の調査では、外国人に対する規制全般について「強めるべきだ」との回答が65%で最も多く、「緩めるべき」は4%だった▼確かに迷惑行為をする外国人もいる。だが、一部の不心得者をもって、「外国人問題」の呼称で全ての外国人を危険視するのはいかがなものかとも思う。「お開き」は、またどこかで出会う約束でもある。言霊の国の住人として、異国の隣人にも、一方的に遠ざける言葉は嫌悪を生むだけのような気がしてならない。(熊)